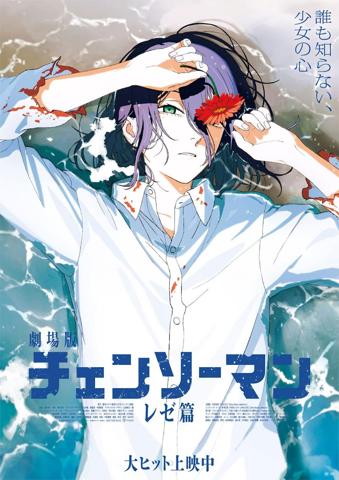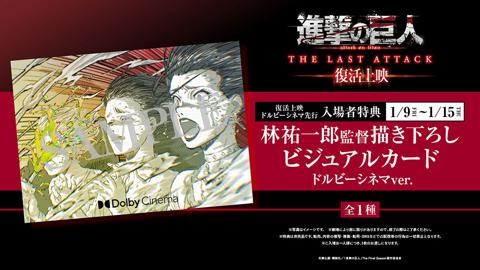SANDA:異色の物語に説得力を持たせる舞台設定 アクの強い絵作り サンタの“赤”にこだわり 霜山朋久監督インタビュー
配信日:2025/11/24 7:01

「BEASTARS」で知られる板垣巴留さんのマンガが原作のテレビアニメ「SANDA」が、MBS・TBSほかの深夜アニメ枠「アニメイズム」で放送されている。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本が舞台の異色の“サンタクロース”ヒーローアクションで、サイエンスSARUによる斬新な表現、板垣さんの力強い絵がそのまま動いているような躍動感のある映像が注目を集めている。アニメを手がけるのは、「ユーレイデコ」「SUPER SHIRO」などで知られる霜山朋久監督だ。アニメならではのこだわりや、制作の裏側を聞いた。
◇現実的で非現実的なストーリー キャラクターの力強さ
「SANDA」は、2021年7月~2024年7月に「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で連載されたマンガ。超少子化時代を迎えた近未来の日本で、国の宝である子どもたちは、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護されており、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物として排除の対象とされていた。中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメートの冬村四織から命を狙われたことをきっかけに、自分がサンタクロースの末裔(まつえい)であることを知り、子どもたちを守るためにサンタクロースとなって大人たちと戦うことを決意する。
物語は、早朝の教室で三田が包丁を手にしたクラスメートの冬村に襲われる……というショッキングなシーンから始まる。霜山さんはその「冒頭の物語のつかみの強さ」に魅力を感じたという。
「三田は、早朝の教室で同級生の女の子に包丁で襲われ、その日の放課後には同級生に刺される。翌日、その女の子は理科の授業で、爆弾をおなかに巻いてくる。今のお話だけ切り取ると、引きはめちゃくちゃ強いけど、作りがちゃんとできていないと、子どもが考えたような雑な話になってしまう。でも、それをちゃんと魅力にできるキャラクターの力強さが大きいと思います。三田は、包丁で襲われたことも、不器用ゆえの好意の裏返しだと、ものすごい勘違いをする。三田自身の思い込みの強さと受け入れる懐の深さもすごいと思いました」
冬村は、三田がサンタクロースの末裔であることを知っており、その力を使って、行方不明になった親友の小野を探すという願いをかなえるために、一見むちゃくちゃな手段をとった。「こういった要素だけを取り出すと、あまり説得力がないようにみえたりもするのですが、そんな派手な部分をキャラクター性の圧と、絵力、要所要所でのいい表情などで面白さにされていて『続きがもっと見たい』と思える」と魅力を語る。
超少子化時代を舞台とした物語の設定については「いい感じに現実的で、いい感じに非現実的」と感じているという。
「超少子化については、今の現実を見ていたら確かにあるだろうなと。子どもが減ったからサンタクロースのことをみんな忘れちゃうという発想の飛躍も素晴らしいなと思いました。また、サンタクロースを伝説の人物ではなく、ある一族の能力に落とし込んでいる。板垣巴留先生は『SANDA』を『少年と大人についてのお話』と語られていますが、三田はサンタクロースになることで強制的に大人になって、またすぐ子どもに戻ります。普通の人間だったら、心の中で子どもと大人を行き来して、その中で大人らしさを身につけていくと思いますが、無理やり強制的に大人になることで、より濃縮されて、物語の魅力になっているのかなと」
◇抑圧的な学園を表現 サンタの特別な“赤”
霜山監督が「SANDA」をアニメ化する上でまずこだわったのは、舞台である大黒愛護学園の描写だった。
「マンガをアニメ化すると、色が付く。それはキャラクターだけでなく、後ろの背景にも色が付きます。キャラクターより背景のほうが面積が広いことが多いので、そこに色が付き、若干荒唐無稽(むけい)さもあるようなシチュエーションの中にキャラクターたちがちゃんと存在しているという説得力をつけるために、学園を丁寧に描写することにこだわりました」
原作者の板垣さんは、東京の伊勢丹新宿店を学園のモデルとしていることを明かしており、霜山監督は「なるほど」と納得したという。
「それを知ってから改めて伊勢丹新宿店を見に行きました。内装は現代的なきれいな感じなのですが、外観は昔ながらの石造りで、重たく、どしーんとしている。舞台になっている学園は子どもを保護しているが、管理しているところでもあり、すごく抑えつけている建物。そういう絵作りがこれだったらできるなと感じました。そこから重さや硬さ、大きさなど、自分が見て感じたものを画面でも反映できたらなと思いました」
物語の冒頭では特に、モノトーンに近い色味にして閉塞感、抑圧感のある学園を表現した。そんな中でより映えるのがサンタクロースの“赤”だ。主人公の三田は、血や赤色の服など、赤いものを身にまとうことでサンタクロースに変身するが、サンタの赤は特別な色として設定したという。
「実は作中では、いろいろな赤が登場します。生徒たちが着る学園のジャージも赤ですし、サンタを捕獲する対抗組織の赤衣の特捜隊も赤です。現実世界でもいろいろな印象の赤があふれています。そうした赤のバリエーションの中で、サンタクロースの赤は、一番ヒロイックで派手な目立つ赤にしたいなと。ほかの赤は、同じ赤でも彩度を変えたり、ちょっと紫方向にしてみたり、緑方向にしてみたり、ちょっとずつ外していって、サンタの赤との差を付けるように気をつけました」
◇キャラクターの存在感を際立たせる サスペンス的な絵作り
霜山監督が語るように、「SANDA」は一癖も二癖もある濃いキャラクターも魅力的だ。アニメでは、板垣さんが描くキャラクターをどのように表現しようとしたのだろうか。
「キャラクターたちを魅力的に見せる上で意識したのはルックとストーリーの中での彼らの振る舞いです。ビジュアルについては、要所要所でいい表情をしているので、それをちゃんと拾いたいと。板垣巴留先生の絵は、力強くて勢いがあるので、線の勢いもアニメで反映できるように頑張りました」
SNSなどでは「先生の絵が動いている」といった反響も上がっているが、マンガの線をアニメで表現するのは難しい部分もあるという。
「あの線のニュアンスは、全部を描いて作っているだけじゃなくて、絵で描いた上にさらに撮影などの処理で一律にエフェクトをかけて線のニュアンスを出しているんです。作画だけでは弱めのニュアンスになってしまうこともあるので、それを撮影処理で補足しています」
ストーリーについては、キャラクターの存在感を際立たせることを意識した。
「キャラクターの存在感を感じるようなシーンでは、原作を初めて読んだ時の印象を再現できるようにと考えています。『SANDA』は、冬村や甘矢(一詩)など、みんなが願いを持ち寄って三田のところに集まっていく物語で、その願いにキャラクター性が反映されているので、そこをうまく描けると魅力的になるかなと」
霜山監督は「見ている人の印象に残りやすい演出、手段を選んでいる」といい、その一つが光と影の演出だという。重要なシーンでは特に、光と影の差がくっきりと表現されている印象がある。
「自分の好みもあるのですが、『SANDA』という作品はドラマチックで、サスペンスの要素があるので、サスペンス的な絵作りがしやすいなと。例えば、まだ陽が昇りきっていない早朝の教室に斜めに柔らかい光が入り、影が差すようなシチュエーションは、青春ものであれば『これから爽やかな物語が始まる』という見せ方ができます。でも、『SANDA』ではそれがサスペンスの始まりになる。三田と冬村が甘矢に拘束されるシーンでも、夕焼けの日差しが“やばさ”を思わせる光になったりする。ドラマの強さがあるので、こってりとアクの強い絵作りができるんです」
霜山監督が語る「アクの強い絵作り」は、サンタをはじめとした迫力あるアクションシーンでも際立っている。アクションシーンでは、スタッフが霜山監督の想定をはるかに超える表現を見せることも多いといい、「アニメーションの集団作業ならではのことで、個人個人の『こういうのが面白い』を持ち寄っていただいた結果、すてきな絵になる。非常に幸運な巡り合わせです」と語る。
今後のストーリーについては「まだいろいろな謎があるので、それがどうなっていくかを楽しみにしていてほしいです。この後も、これまで登場してきたキャラクター以上に癖の強いキャラクターが出てきます。映像的にも見どころいっぱいで作っていますので楽しみにしていただければ」と語る。三田、サンタクロースたちの活躍に注目したい。
提供元:MANTANWEB