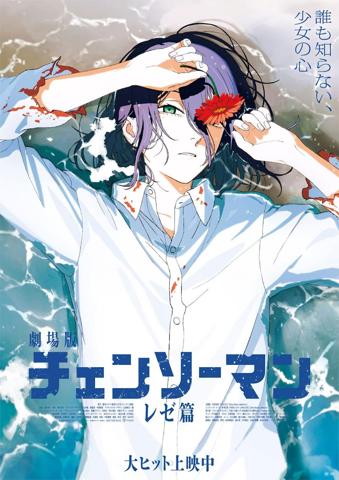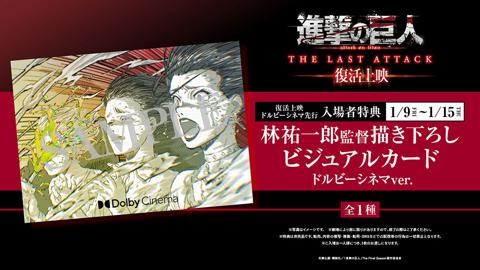果てしなきスカーレット:細田守監督インタビュー 「時かけ」から19年 未来像の変化 「生と死」を描く挑戦
配信日:2025/11/21 7:01

「時をかける少女」「サマーウォーズ」などで知られる細田守監督の最新作となる長編アニメーション作品「果てしなきスカーレット」が、11月21日に公開された。2021年7月公開の前作「竜とそばかすの姫」以来、約4年ぶりとなる新作で、テーマは「復讐」「生と死」。国王である父を殺した敵(かたき)への復讐に失敗した主人公の王女・スカーレットは、《死者の国》で目を覚まし、現代の日本からやってきた看護師の青年・聖と時を超えて出会い、共に旅をすることになる。少女と青年が時を超えて出会うという構図は、約19年前の2006年に公開されたヒット作「時をかける少女」と同じだが、作品のテイストは全く異なる。細田監督が19年間の変化と、最新作での挑戦について語った。
◇生と死が混じり合う《死者の国》 「現世のように描くべき」
「果てしなきスカーレット」は、細田監督が原作、脚本を手掛ける。舞台は中世で、復讐に燃える王女が《死者の国》を旅する……という世界観は、これまでの細田監督作品とはかなり毛色が違い、制作発表当初から話題を集めた。主な舞台となる《死者の国》は、生と死が混じり合う場所で、人々が略奪と暴力に明け暮れ、力のない者や傷ついた者は虚無となり、その存在が消えてしまうという狂気の世界。細田監督は今作で「生と死」を描きたかったといい、「こんな大きなテーマに挑むことになるとは思わなかった」と語る。
「これまでの作品の中にも少なからず『生と死』の要素はあったとは思いますが、今回、よりそれを真正面から描こうと腹を括りました。大きなテーマに挑むからこそ、より大きなスケールの映画になったところもあると思います」
「生と死」を描こうとしたきっかけは「コロナになって、死を意識せざるを得ない状況を体験した」ことだという。作中でスカーレットと共に旅をする青年・聖を看護師の設定にしたのも、当時入院先で接した看護師の存在が影響しているという。
「スカーレットは復讐者ですから、一種の現実主義者なんですよね。聖という理想主義者が横にいることによって対比が生まれるんじゃないかと思った時に、聖のキャラクターとしての職業で最初に浮かんだのが、利他の精神に満ちた看護師さんたちの姿だったんです」
そんなスカーレットたちが旅する《死者の国》は、砂漠が広がる荒涼とした世界だが、現実世界と似ている部分もある。どのように死者の世界を表現しようとしたのだろうか。
「日本にも地獄絵図がたくさん残っていますが、この作品で地獄を表現する上で、日本美術の研究者に『日本の中世の地獄はどうやって描かれているのか』という話を聞いたんです。すると、その研究者は『これは地獄のように見えて、実は現世を描いている。中世当時の生きるのが辛い現世を描いているんだ』と言うわけです。その話を聞いた時に『なるほど』と思わず膝を打ちました。それを受けて、この作品では『生と死が混じり合う場所』を、地獄的にファンタジックに描くのではなく、むしろ現世だと思って描くべきだと思ったんです。たとえば紛争のニュースなどでも『ここはまるで地獄のような光景です』とレポートされるように、現世にだって地獄はあって、僕らはそういう中で生きている。そんな中でも、魂が天国に行ければと願っている人が大勢いる。それをちゃんと描きたいなと思いました」
細田監督は、《死者の国》を描く上で、ヨルダンやイスラエルでもロケハンを行ったといい、「ヨルダンの荒野の中で、かつてどのように宗教的なものが育まれたのか、原風景みたいなものも見ることができた。それも、この映画の中に色濃く反映されていると思います」と語る。
◇初のプレスコで感じたアニメの可能性
「復讐」「生と死」という壮大なテーマを描く今作は、細田監督作品初の試みとなるプレスコという手法で制作された。声を先に収録し、その声に対してアニメーションを制作していく手法で、「今回、多くのCG技術を導入する上でプレスコのほうが表現のメリットが大きいと思い、選択しました」と説明する。最初に収録をしたのは、スカーレットの敵であるクローディアス役の役所広司さんで、細田監督はその演技に圧倒された。
「ものすごかったんです。クローディアスの力強さと憎らしさ、ずる賢さ、哀れさをすごい表現力で演じられていて、特に最後のシーンは、収録しながらその演技に鳥肌が立つほどでした。この映画のテーマである『生と死』の極限までいった人間が出す声は、こういう声ではないかと思うくらい。すごいと思ったと同時に、これを画(え)にするのは果たして可能なのか? 無理なんじゃないか?とも感じました。その後にスカーレット役の芦田愛菜さん、聖役の岡田将生さんの収録をしたのですが、役所さんのお芝居を聞いた後ですから、すごいプレッシャーだったそうです。しかし結果的にはそれに負けないほどのすばらしい演技をしてくれたので、本当に良かったと思います」
収録の後には、声の芝居を映像で表現するアニメーターに驚かされたという。
「俳優たちの芝居を受けて、アニメーターのみんながすごく刺激を受けて奮い立ったんです。何度も繰り返し細かく動きを作り込んで、素晴らしい芝居を見せてくれました。結果的に俳優のみんなとアニメーターのみんなが力を合わせていい芝居を作ることができて、アニメーション表現の可能性を大きく感じましたね」
◇「時をかける少女」との違い 若者への思い
「果てしなきスカーレット」の制作発表の際、「『時をかける少女』から19年。衝撃のヒロイン誕生」というコピーが添えられた。新作は細田監督が「復讐」「生と死」という壮大なテーマに挑んだ意欲作だが、少女と青年が時を超えて出会うという構図は「時をかける少女」と似ている。細田監督自身は「『時かけ』と似ていることに、制作の途中で気が付きました」と振り返る。
「たしかに、未来から来た男性と過去の女性が主人公という構図は同じですよね。物語のその時代を生きる女性が、未来を向いて歩んでいくところも同じではないかと思います。ただ、構造は同じだけど、描いていることも同じかというと、少し違う。19年前の『時をかける少女』と『果てしなきスカーレット』の何が違うかというと、“未来観”が違うんです。『未来をどのように感じているか』ということが、この19年の間に大きく変わったのではないかと思うんです」
「時をかける少女」は、1967年に発表された筒井康隆さんの小説を原作としており、小説と劇場版アニメではストーリーが異なるが、「それは1960年代と2000年代では、まさに未来観が違うから、必然的に結論が変わるだろう、ということで作ったわけです」と説明する。
「では、『時をかける少女』と『果てしなきスカーレット』ではどのように変わったか。2006年の『時をかける少女』を作っていた頃は、ちょっと希望があるような未来観として描いた。若い人のバイタリティーによって『未来を作ってほしい』という願いを込めて作った。それに対して2025年の今は、若い人にそこまでバイタリティーを求められる時代なのか?という気がするんです。SNSやAIが社会や個人に大きな影響を及ぼすようになり、無責任に若い人に『頑張れ』って言えない。それほどに時代が変化している」
現代の若者は「いろいろなものにがんじがらめで、不自由に思える」とも感じているという。
「行き先が見えない世界で、今まで正しいと思っていたものが少しずつ変わっていく時代なので、若い人が不安に思うのも無理もないですよね。以前のように『頑張れ』と言うだけじゃなく、その不安に寄り添うことが大事。その上で、彼らにとって力になるような映画になればいいな、と思いながら作りました。迷っていたスカーレットが、自分は本当はどうやって生きていきたいのか、ということを探そうとする姿に、みなさんの今の気持ちを重ね合わせて見てほしいですね」
提供元:MANTANWEB